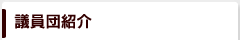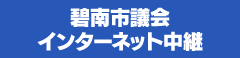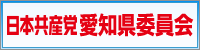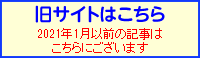誰もが補聴器を買えるようにしてほしい―。そんな声が広がり、独自の助成を行う自治体が、増えています。
愛知県でも2025年度から8市町村が補助を実施していることが明らかになりました。
聞こえるようになり“集まりにも行ける
小さな声や騒音下での会話の聞き間違いや聞き取り困難を自覚する。会議などでの聞き取り改善目的では、補聴器の適応となることもあります。
厚生労働省は2021年、自治体の補聴器助成の状況などを調査した「難聴高齢者の社会参加等に向けた適切な補聴器利用とその効果に関する研究」を公表。当時、助成は36自治体、65歳以上の住民の聴力検査は4自治体のみが実施との結果をふまえ、「取り組み強化の検討が求められる」と提言しました。
補聴器をつければ生活の質が上がるのは確実だが、購入するまでがかなりハードルが高いのは価格の問題もあります。
東京都港区で13万円補助
東京都港区では、補聴器相談医が補聴器の装用を必要と認めた60歳以上の住民に、13万7千円まで助成します。(住民税課税者には2分の1)制度を始めた22年度の利用は523人と、当初の見込み220人を大きく上回りました。
担当課は「医師会や補聴器販売店とも相談して助成額を決めた。初期には13万7千円以内の補聴器で十分適応する人も多いので、自己負担なく買えることが、申請の多さにつながったと思う」と話します。住民からは「制度があったから購入できた」「聞こえるようになり、集まりにも行けるようになった」などの声が寄せられたといいます。
碧南市でも、補聴器助成をさらに広げるとともに、聴力検査での早期発見、補聴器を使い続けるための支援を含め、難聴対策の保険適用をめざし運動を進めましょう。