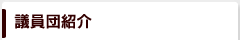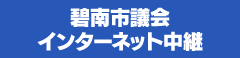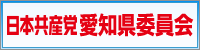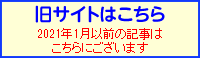未来と希望を奪う「搾取」
日本の労働者への搾取が強まっています。
2024年度の大企業の売り上げから経費を引いた経常利益は、第2次安倍晋三政権が始まった12年度と比較して2・6倍になりました。法人税減税が繰り返されたため、経常利益から税金等を引いた純利益は4・6倍にもなっています。株主への配当も2・8倍と大幅に増やしましたが、従業員の給与は1・1倍とほとんど伸びていません。
大企業わずか37%
生産過程で新たに作りだされた付加価値のうち、人件費に支払われる割合を示す労働分配率は大きく低下しています。9月1日、財務省が発表した「法人企業統計調査」によると、2024年度の労働分配率は1973年度以来、51年ぶりの低水準です。
企業規模別で労働分配率を見ると、中小企業が75・6%なのに対し、資本金10億円以上の大企業ではわずか37・4%にとどまります。労働分配率の推移を見ると中小企業がほとんど変わらないのに、大企業では2012年度の53・4%から大きく低下しています。
38ヵ国中、11位の日本
「朝日」2月12日付は、労働分配率の推移の国際比較を紹介した記事で、日本は1996~2000年、OECD38カ国中4位で、米国、ドイツ、フランス、英国といった主要先進国より頭一つ抜け出していたものの、16~20年平均では主要国の後塵(こうじん)を拝し、38カ国中11位に後退したと指摘しています。
低賃金、非正規の増加
労働分配率の大幅減少の原因のひとつが、低賃金の非正規雇用の増加です。
総務省の「労働力調査」によると、非正規雇用の労働者は1985年の655万人から2024年には2126万人へ3・2倍になり、労働者全体の37%を占めます。
自公の規制緩和が原因
財界要求に応えた自公政権などが労働法制を規制緩和したからです。
非正規が製造業に拡大
1985年に労働者派遣法が成立して以来、95年には対象業務がそれまでの16業種から26業種に拡大しました。99年には一部を除き原則自由化され、2003年には製造業にまで拡大しました。さらに安倍政権は15年、人を入れ替えたり、部署を替えたりすれば、派遣先企業は派遣労働者を無期限に使い続けることができる「生涯派遣」の制度にしてしまいました。
悪循環を抜け出す
人件費の抑制は、個別企業ではコスト削減により競争力が強化されるように見えますが、全体では消費が減り経済が停滞します。
一方で“株主至上主義”の新自由主義経営がもてはやされ、多くの株を持つ大株主や富裕層に富が集中し、格差が拡大してきました。
過去最高の利益、大企業に
日本経済が「失われた30年」と呼ばれる長年の低迷から抜け出せない原因は、消費と売り上げの低迷にもかかわらず、大企業が過去最高の大きな利益をあげ、株主への配当を優先するため、さらなるコスト削減に走り、下請けをたたき、人件費を抑制するという悪循環にあります。
社会主義は搾取から抜け出す道
打開の道は、この強欲資本主義の悪循環を脱し、労働者の作りだした富をその手に取り戻し、大幅な賃上げを実現することにこそあります。
今、日本共産党の発行する「いま資本論がおもしろい」が日本農業新聞にも紹介されました。